近年、福利厚生の一環として「借り上げ社宅制度」を導入する企業様が増えています。
人材確保や福利厚生(社員様の生活支援)の一環として活用されるケースが多いですが、その運用で意外と見落とされがちなのが「社宅使用料」の取り扱いです。
「社宅使用料って何?」「会社が払っている家賃とは別なの?」と疑問に思う方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実はこの費用、設定方法を誤ると従業員とのトラブルや税務上のリスクを招く可能性もあります。
そこで今回は、社宅使用料の基本的な考え方から、計算方法、社内規定を作る際の注意点、設定事例までをわかりやすく解説します。
これから社宅制度を導入予定の企業様はもちろん、既に導入済みのご担当者も今一度確認しておきたい内容です。借り上げ社宅制度の運用を見直したいと考えている人事・総務・労務ご担当者の方は、ぜひご参考くださいませ。
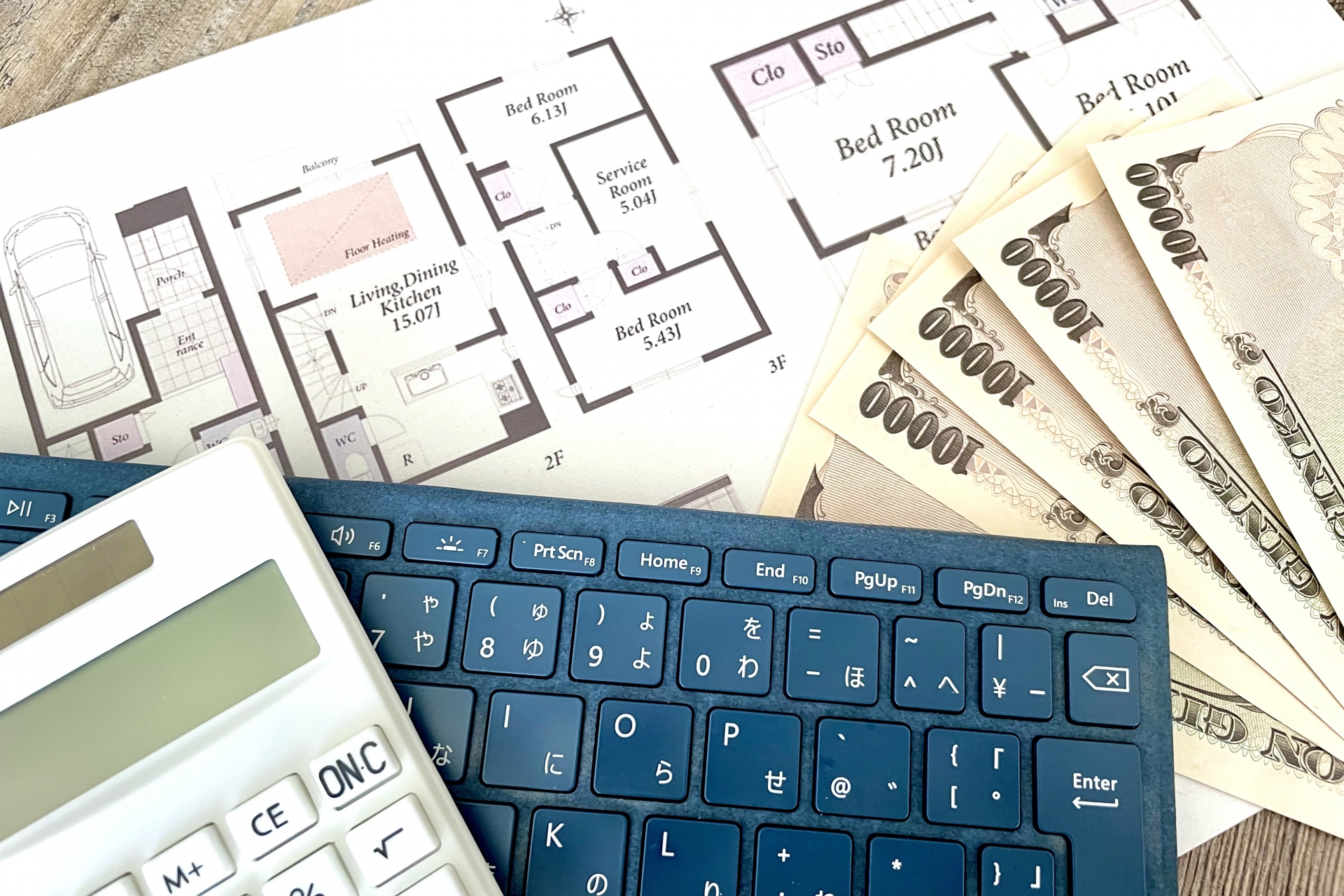
─ 目次 ─
(1)社宅使用料とは?
─制度の背景
(2)社宅使用料の計算方法
─賃貸料相当額の算出方法
(3)規定作成時の注意点
─正当な規定が法的リスクを回避する
(4)他社はどうしてる?設定事例と傾向
─業界による負担割合の違い
─自社の状況にあてはめて設定しましょう
まとめ|社宅使用料は“制度の信頼性”を支える大事なポイント
社宅使用料とは、会社が用意した社宅を社員様に貸与する際に、社員様から徴収する費用のことを指します。
あくまで会社が負担している賃料の一部を入居者が支払う形であり、社員様に全額を請求するものではありません。
もし"会社から提供される住宅を無償で利用している"とみなされると、給与として課税対象になってしまう税務上のルールがあります。
そこで一定額の社宅使用料を徴収することで、課税対象外の福利厚生としての扱いを受けられるようにしているのです。
つまり社宅使用料は、会社にとっても社員にとっても税負担を最小限に抑えられる仕組みのひとつ。正しく理解し、適切に設定することが制度運用のカギとなります。
社宅使用料の設定にあたっては、国税庁が定める「賃貸料相当額」を下回らないことが重要です。
これを下回ると差額が給与とみなされ、所得税や社会保険料の対象となる可能性があるため十分ご注意ください。
以下の3項目の合計で算出します。
(国税庁サイト:「使用人に社宅や寮などを貸したとき」より抜粋)
借り上げ社宅(=会社が民間物件を賃貸して社員に貸与している形)の場合は、上記に代えて「家賃相場の50%以上」など、一定の合理性があれば税務上認められるケースもあります。
とはいえ、独自に金額を設定するとリスクがあるため、税理士や社労士に確認しながら進めることをおすすめします。
社宅使用料を運用するうえで欠かせないのが、明確な社内規定の整備です。特に人事・労務・総務ご担当者様にご注意いただきたいのは、「就業規則」や「福利厚生規程」との整合性です。
下記を明文化しておくことで、社員とのトラブルを防ぎやすくなります。
税務調査においては「規定があるかどうか」「内容が妥当か」も確認されるポイントです。
文書として残し、運用と一致させておくことが、法的なリスクの回避にもつながります。
そのため導入済みの企業様においても、年に一度は見直しを行うことをおすすめします。

では、実際に他の企業は社宅使用料をどのように設定しているのでしょうか?
一般的には、「家賃の3割〜5割」を社員負担とするケースが多く見られます。月額10万円の賃貸物件を会社が借り上げた場合、社員負担は3万円〜5万円程度ですむイメージです。
若年層の採用競争が激しいIT系業界では、社員負担を「1割程度」とする企業が他業種と比べて多い傾向です。
入社したばかりで給与の低い時期、家賃の自己負担を抑えられるのは若年層にとってありがたいですね。
一方、制度全体を福利厚生の一部と位置づけてバランスを重視する製造業などでは、社員負担が「5割以上」の設定も珍しくありません。
社宅を利用していない社員様と大きな格差が生まれないよう配慮されています。
首都圏と地方でも家賃水準が異なるため、設定額も柔軟に調整している企業様は多いです。
最近では「勤続年数に応じて使用料が変わる」など、長期勤務を促す工夫も見られます。
他社の傾向を知ることで、自社の制度設計にも納得感のある改善ができるでしょう。
社宅使用料は借り上げ社宅制度を適正に運用するうえで欠かせない要素です。
設定金額が適正でなければ、社員との不信感や税務上のリスクにつながることもあるため、十分な注意が必要です。
本記事では、以下のポイントを解説してきました。
制度を導入して終わりではなく、継続的に見直し、社員様にとっても企業様にとっても納得のいく形で運用していくことが大切です。
この記事が、社宅制度をより効果的に活用するヒントになれば幸いです。
プレニーズでは借り上げ社宅の管理運用についてのお悩み相談を受け付けております。
……などなど、借り上げ社宅に関わるご相談を受付中です!皆様のご連絡お待ちしております。
株式会社プレニーズ神田店
営業時間 09:30-18:30(土日・祝日を除く)
TEL :03-6384-0415
FAX :03-6384-0416
★【用語解説】借り上げ社宅に必要な「2つの契約」とは
★「どんな部屋を借りるべき?」社宅規定の作り方~お部屋探し編~
★社宅の自社管理、こんな“困った”はありませんか?
サービス・製品に関してお気軽にお問合わせください
© 2020 pleaneeds CO., LTD